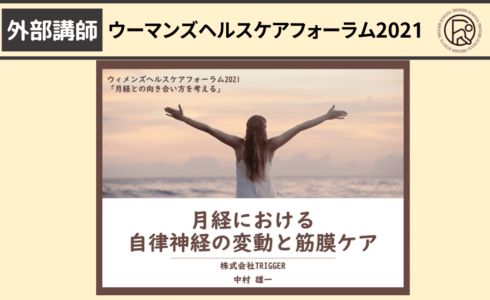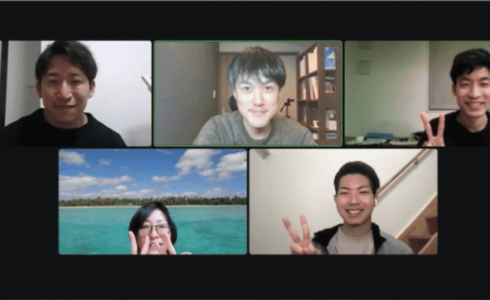筋膜調整で脂肪の蓄積をコントロールする!『自律神経と栄養』研修で講師を務めました。
筋膜調整セラピスト
トリガースクールの中村です。
7月27日(日曜日)
広島スパインダイナミクス療法研究会さま主催の研修会,『自律神経と栄養』シリーズの第1段として講師を務めました。
脂肪の過度な蓄積や消耗による体型の変化は、情報過多の時代になり、よりコントロールしていくのが難しくなったと言っても過言ではないと思います。
今回は研修会の内容をダイジェスト版でシェアします。
人はなぜ太るのか?
前半は富永先生による『人はなぜ太るのか?』をテーマに、自律神経と心理学の観点から原因と対策のお話。

富永先生は理学療法士の資格を持ち、不調を予防するために体質改善の重要性を伝えるために整体サロンを経営しながら、自律神経やホルモンバランスを調整しながら健康的に体重・体型を調整していく「食欲コントロール・ダイエット」を独自に考案。現在は食欲コントロール・ダイエット協会を立ち上げ、より多くの方に情報発信を行っています。
自律神経を整える食材なんてない!
富永先生いわく、「自律神経を整える食材は存在しない」ということ。

基本は、規則正しい生活がベースにあって、活動と休息のバランスを取りながら、無理をせずに体重をコントロールしていくことが重要なのだと。
体重が増えてしまう原因のほとんどが「食べすぎ」によるものなんです。
え?そんな当たり前のこと?
だったら我慢すればいいじゃん。
そう思った方もおられるかもしれませんが、実はこれがそんなに甘くないんです。
「食べすぎて」しまう根本原因は一人ひとり違って、一筋縄にはいかない。
この根本原因に自律神経とホルモンバランスの乱れが複雑に絡み合っているので、解決はより難しくなるんです。
自律神経とダイエットの関係
自律神経が乱れると、食事のパターンや食事から得られるエネルギーの吸収と消費、いわゆる代謝バランスが大きく乱れます。
例えば、夜遅くまで仕事をして睡眠時間が短くなったり、寝る間際までスマホやタブレットを見て寝付きや睡眠の質が悪くなっていたとします。
これは、興奮状態を促す交感神経の活動が活発になっていることを現し、休息状態を促す副交感神経の働きが弱まっていると考えられます。
脂肪から分泌されるレプチンというホルモンがあるのですが、このホルモンの分泌は1日にの中でも夜間〜早朝にかけて分泌量が最大となります。実は、このレプチンというホルモン。脳に食欲を抑えるように司令を送るための非常に重要なホルモンなんです。

ヒトは脂肪が増えてくるとレプチンの分泌を増やして食べる量を減らしたり、脂肪を分解してエネルギーに変えるように脳に働きかけるというように、脂肪が過剰に増えないように自動的に調整できるようになっているのです。ですが、夜中も夜通し起きている状態がつづくと、食欲を抑えたり脂肪分解を促すレプチンの分泌が少なくなります。
さらにそれだけでなく、食欲を増すグレリンというホルモンは逆に増えてしまうのです。
今回は交感神経の活動が活発に鳴ることで睡眠不足となり、その結果、食欲が抑えることができなくなり食べ過ぎる習慣がついてしまうというケースを紹介していただきました。

ストレスとダイエットの関係
ストレスで食べすぎてしまう・・・
よく耳にすると思いますし、思い当たる方も多いのではないでしょうか。
では一体、なぜストレスで食べすぎてしまうのでしょう?
精神的・心理的なストレス(※1)が加わると、脳の視床下部から下垂体を経て、副腎からコルチゾールというストレス耐性ホルモンが分泌されます。コルチゾールは危機的状況に対して、血圧や心拍数を上げて闘うか逃げるかに備えさせる役割があります。
さらに、コルチゾールは筋肉や脳に栄養を送るために血液中に糖分が増えるように作用し、血糖値を上げてしまうのです。
血糖値が上がるとい血糖値を下げるためにインスリンが分泌されます。インスリンの役割はエネルギーを蓄えることなので、脂肪の蓄積を促します。
危機的状況が回避されればコルチゾールの濃度も下がります。さらに活動によって糖が使われるので血糖値も下がるはずなんです。
ですが、現代社会では慢性的かつ持続的なストレスがほとんどです。

上昇した血糖値を十分に消費するだけの活動量もありません。
そうなると何が起きるか?
コルチゾールの濃度、血糖値、インスリン分泌量の全てが高いままになり、それでも血糖値を下げようとさらにインスリンの分泌が増えてしまい、インスリンに対する感度が落ちてしまう「インスリン抵抗性」がついてしまうのです。
インスリンはエネルギーを蓄えるのが役割の1つなので、慢性的に脂肪が蓄積してしまう悪循環に陥ってしまうのです。(※1:ストレスとは、本来は自分の外側から向けられるあらゆる刺激に対して使われます。悲しみ、怒り、寂しさなどのネガティブな要因だけでなく、嬉しさや楽しさ、または気候や気温の変化なども全てす自分にとってはストレスです。)
ダイエットを始める前にまずやるべきこと
ではダイエットを始めるにあたって、まず何からするべきなのでしょうか?
それは
「食べすぎてしまう原因を自分なりに観察すること」です。
食べすぎてしまう要因は先程の例以外にもたくさんあるのですが、食べすぎてしまった時に、ふと考える時間を設けてみましょう。
睡眠の質や量はどうだったかな?
最近イライラしてたかな?
ストレスが溜まったら発散する方法は食べる以外で何かあるかな?
など、食べる前に陥っていた自分自身の状況や環境を一度冷静に分析してみましょう。

それによって、自律神経やホルモンバランスの乱れにいち早く気づくことができます。
ダイエットは、短期間で何かを我慢して強制的に体重を減らすのではなく、
まずは乱れている自律神経やホルモンのバランスを整えて、食べすぎない状況を作ってあげることが大切です。
それを抜きにして、無理やり体重を落としたところで、そもそものヒトとしての生命維持活動の調整が乱れている以上、リバウンドは免れないと思います。
筋膜調整で脂肪の蓄積とコントロールする?
午後からは私のパートです。

手を使った筋膜の施術で脂肪の蓄積をコントロールすると聞くと、驚かれる方も多いとおもいますが、これも、筋膜と自律神経の関係を紐といて行けば、理解できるのです。
鍵は脂肪組織の働きにある
そもそも脂肪とは?ということから解説していきました。

脂肪と聞くと悪者にされることが多いのですが、ヒトの体にとっては非常に大切な役割があります。
脂肪組織から食欲を抑えるレプチンが分泌されるのは先程お伝えした通りですが、レプチンの分泌が正しく行われるにはある条件があります。
一体なにか?
それは、脂肪が正しく働くことです。
ヒトの細胞は伸び縮みなどの刺激が加わった時にスイッチが入って活動が活発になります。もちろん脂肪も同じです。
なので、脂肪組織が十分に動くだけの柔軟性、脂肪と脂肪の間の滑りやすさ、伸び縮みなど、とにかく脂肪が柔らかくないとだめなんです。
脂肪の動きが悪くなると、吸収と消費といった代謝回転が悪くなります。代謝回転が悪くなれば、脂肪はどんどん蓄積され、肥満になります。
脂肪が増えれば、レプチンの濃度も増えますが、脂肪が溜まってしまう原因が解決されずどんどん増えていくと、レプチンの分泌はさらに増え、最終的にはレプチンに対する感度が悪くなる「レプチン抵抗性」の状態となり、食欲を抑えることが難しくなってしまうのです。
脂肪の動きが悪くなる原因とは?
では脂肪の動きはなぜ悪くなってしまうのでしょうか?
考えられるのは、大きくわけて2種類です。
1つはケガや骨折、手術などの外からのダメージです。
炎症や局部的な脱水によって、脂肪の動きは悪くなります。

もう1つは、内臓の不調です。
主には胃や腸などの消化器のトラブルと代謝を司る内分泌器のトラブルです。
内分泌器は甲状腺や肝臓を含んでいるため、それらの臓器への負担や不調がもともと存在する場合は脂肪の蓄積を増やしたり(時に急激に消耗させたり)するため、脂肪細胞が大きくなり、数も増えてしまい、動きが悪くなります。
さらに、脱水、炎症、pHの酸性化は脂肪組織の間に潤滑剤として存在しているヒアルロン酸の粘性も変化させてしまいます。

本来であればスベスベの性質であるヒアルロン酸がベトベトの水のりのような性質に変化してしまうことでも、脂肪の動きが悪くなってしまうのです。
脂肪の動きを良くする方法とは?
悪くなってしまった脂肪の動きを良くするにはどうすればいいのでしょうか?
実はシンプルです。
動きの悪い箇所を見つけて、動くようになるまでほぐしていくのです。

この時、圧迫と摩擦を加えて若干の炎症を引き起こします。
炎症を促すことで熱が生まれ、酵素の働きによって脂肪やヒアルロン酸の分解と再生が促進されます。
それによって、大きくなった脂肪は小さく、数が増えた脂肪細胞は少なく、そして、ヒアルロン酸をスベスベの状態へ戻していくことで、脂肪間の滑りやすさが回復していくのです。
過剰な脂肪の蓄積は、代謝異常の結果として起こっていることが多いのですが、脂肪組織そのものの機能が落ちてしまうと、脂肪の消費を支持する内臓の働きも十分に機能しなくなります。
そのため、体の中からだけでなく、脂肪組織そのものをターゲットに介入することも一つの要素として重要になるのです。
概論を説明したあとは、みなさんで実技です。

動きの悪い脂肪は硬いだけでなく、痛みを伴う場合が多いです。

参加者のみなさんも、痛い場所と痛くない場所があったり、人によって脂肪の質感が全く違うのを体感していただけたかと思います。
まとめ
過度な脂肪の蓄積や消耗は、自律神経やホルモンバランスに大きく影響されています。
まずはそのことを理解して、自律神経の乱れを調整していくことから始めましょう。
さらには、脂肪そのものの動きが悪くなるだけでも代謝に影響を与える場合があります。
今回は、体の内側からの対応を富永先生、体の外側からの対応を私の方で担当させていただきました。
大切なのは、1つの手法や考え方に執着しないこと。
だれかが成功したからと言って、自分も同じ方法が合うとは限りませんよね。
とにかく、何かを我慢してストレスを溜めながら実践するのではなく、無理なく健康的に体重・体型をコントロールしていきましょう。

参加してくださった皆さま、主催の広島スパインダイナミクス療法研究会のみなさま、ありがとうございました!
今後も、筋膜調整の可能性をたくさんの方に知っていただけるよう活動していきます!
TRIGGER School
中村
=======================================
現在,募集中のセミナーはこちら▼

※今年最後の週末開催 残席わずか!
(終了しました)*8/17 バネ指・腱鞘炎に対する筋膜調整セミナー@金沢

(終了しました)*9/14 カーラ教授 特別講演会「Fasciaとウィメンズヘルス」

残席わずか!
(終了しました)*8/31-9/1 顎関節に対する筋膜の評価と治療