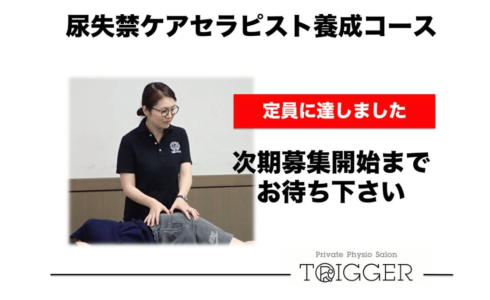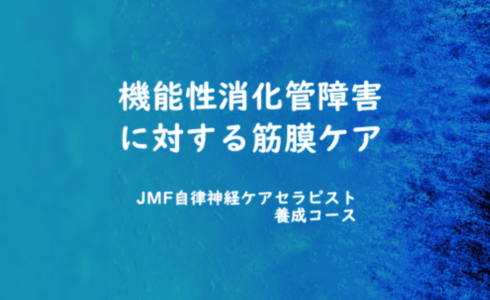第6講義が終了しました!@JMF3期
トリガースクール講師の中村です。
1月15日にJMF3期の第6講義が終了しました!

第5講義のテーマは『施術効果を持続させるための簡単セルフケア』です。
自律神経が乱れている場合、施術による介入はとても重宝します。
ですが、それだけですべてが上手くいくわけではありません。
やはりクライアントさん自身にも体を動かしてもらい、
できるだけ良い状態を保ったり、
再び悪くならないようにケアしていただくと、
より良い状態へとつながっていくことがとても多いのです。
というわけで、第6講義でお伝えするセルフケアは大きく4種類

①背骨の柔軟体操
②ストレッチ
③呼吸エクササイズ
④サボり筋エクササイズ
になります。
自律神経を整え、良い状態を維持していくには、どれも欠かせない要素になっております。
まずは背骨の柔軟体操です。
背骨の柔軟性を維持・向上させていくことで色んな効果が期待できます。

コースでは20種類の体操をお伝えしております。
例えばこちら▼

オーソドックスな胸椎の回旋運動です。
小難しい体操をお伝えしてもクライアントさんはほとんど実施してくれません。
手軽にサクッとできるメニューからでもOK。
大切なことは”継続”です。
次にこちら▼

両膝を抱えながら横方向に転がりつつ、首をしっかり捻る体操になります。
頸部や胸部の動きを促すのはもちろんのこと、実は平衡機能に影響する前庭系も刺激しています。
前庭系と自律神経は一見関係なさそうですが、めちゃくちゃ関係あります。
前庭系の機能が衰えると、外部環境の情報を得るために他の感覚器で代償しようとします。
その代償先の1つが体性神経系になります。
つまり皮ふや筋の感覚受容器が敏感になりやすいんですね。
感覚器が敏感になると、外部刺激にも敏感になります。
それによって自律神経系の過剰興奮にもつながる可能性があるんです。
なので前庭系の機能もしっかりと刺激して、良い状態を保っておく必要があるのです。
続いて、ストレッチです。
ストレッチの狙いはこちら▼

リラックス目的でストレッチを指導する方は多いですが、目的は沢山あります。
ストレッチだけでも色んな効果が期待できるので、しっかりと指導できるようになりたいところですよね。
ストレッチしてほしい筋肉たちはどんな部位かというと・・・

この緑色で塗られた部位になります。
これらの筋肉は発達学的に優位になりやすい傾向にあり、
また臨床的に交感神経が活性化するととても硬くなる印象を持っています。
なので、これらの筋肉を選択的にストレッチできるようコースでお伝えしています。
次に呼吸エクササイズです。
呼吸エクササイズの目的はこちら▼

呼吸の目的もさまざまです。
腹式呼吸は自律神経を整えるためにとても役立ちますが、それだけではダメです。
呼吸数や呼吸パターン、呼吸の変化がもたらす生理学的な反応まで意識して呼吸エクササイズを指導できるようになってほしいのです。

呼吸エクササイズ中は舌の位置を口酸っぱく指導しています。
舌の位置1つで呼吸パターンが変わってしまうので、味方につけておかないと十分な効果が得られない可能性もあるからです。
受講生の皆さん、エクササイズ中はずっと舌の位置と鼻呼吸を意識されていて、素晴らしかったです!
そして最後が『サボり筋エクササイズ』
自律神経系の講習会では珍しい”鍛える”というカテゴリーです。

整えたら終わりのイメージが強い自律神経ケアに、なぜ鍛える要素が必要なのでしょうか?
答えは簡単です。
弱っているところは弱いままだからです。
弱っているところがあると、どうしても強く使いやすい部位に負け、バランスが悪くなります。
そして使いやすい部位はどんどん硬く強くなります。
このバランスは硬いところをほぐしたりストレッチするだけでは良くなりません。
なので、弱っているところは使えるように鍛える必要があるんです。
鍛えるといってもムキムキになるまで強くする必要はありません。
硬くなりやすい、使いやすい筋肉群とのバランスが取れていたらOKなのです。

その変わり、こんなシンプルな運動であってもはじめは意外とキツく感じるはず。
使えてくると姿勢整い、呼吸もしやすいなるので、自律神経は乱れにくくなるはずです。
最終的には有酸素運動能力も高めていくことを指導しています。
これもかなり大事な要素なので、また機会と見つけて解説していきますね!