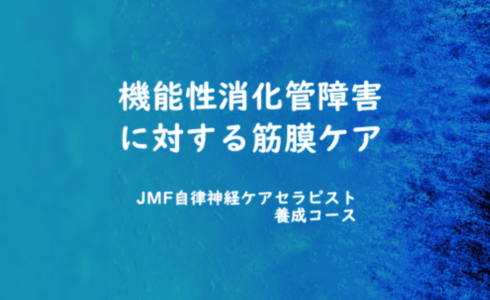コース第4講義を開催しました!@第4期JMF自律神経ケアセラピスト養成コース
皆さん、こんにちは!
トリガースクールの中村です。
12月10日(日)にJMF自律神経自律神経ケアセラピスト養成コース4期の第4講義を開催いたしました!
第4講義のテーマはこちら

神経筋反射テクニックを使って筋肉の緊張を緩めていく方法を学んでいきます。
第3講義では体幹の関節にアプローチすることで体全体の緊張を緩和させる方法を学びましたが、やはり部位によっては反応が不十分なところもあります。
そんな時は第4講義でお伝えする緊張緩和テクニックが重宝します。
緊張性システムと相動性システム
我々の体にある筋肉群は発達学的に大きく2種類に分けられます。
1つが発達学的に古い「緊張性システム」、もう1つが発達学的に新しい「相動性システム」です。
 引用:Phil page, Clare C. Frank, Robert Lardner(著),小倉秀子(監訳),ヤンダアプローチ(三輪書店:2013)
引用:Phil page, Clare C. Frank, Robert Lardner(著),小倉秀子(監訳),ヤンダアプローチ(三輪書店:2013)
緊張性システムは発生学系に古い筋システムで、赤ちゃんがお母さんのお腹にいるころから使われるような、生まれながらにして優位な筋システムであり、主に屈曲筋群がコレに該当します。
そのため、力も入りやすく使われやすいため、しばしば硬くなったり、持続的な筋肉の緊張によって筋肉自体が短くなりやすい反面、萎縮しにくいといった特徴を持っているとされています。
一方、相動性システムとは発生学的に新しいシステムとされており、主に伸展運動において優位となり、姿勢安定筋として重力に対して働く筋システムです。
私自身、この筋システムの分類は自律神経が乱れている場合の特徴にも似ていると考えており、特に交感神経活動が過剰な場合、系統的に古いシステムに頼った屈筋優位の姿勢や動きのパターンに陥っていることがしばしば見受けられます。
つまり、自律神経の乱れている方は硬く短くなりやすい緊張性システムの筋群は優勢となり、やわらかく萎縮しやすい相動性システムの筋群は劣勢になりやすいと考えています。

陥りがちな姿勢とは
崩れた筋バランスは姿勢にも影響を与え、そのせいでいつも似たような姿勢になりがちです。
それがこちら

絶対に当てはまるというわけではないですが、自律神経が乱れている方も黄色で囲っているような部位は硬く、青色で囲っている部位は弱くうまく力が入らないような状態になっていることが多い印象です。
これらのバランスはお互い影響し合っていて、黄色で囲っている短くなりやすい緊張性筋群が優位なほど、青で囲っている相動性筋群は抑制されがちなんです。
つまり、緊張を緩めて動きやすいカラダを獲得するには、硬くなっている緊張性筋群は緩めていきながら、弱ってしまっている相動性筋群はしっかりと刺激を入れていく必要があるんです。
そのため今回の第4講義では、緩める方法だけでなく、鍛える方法の両方を解説していくことになっています。
習慣的な姿勢や動きを観察する重要性とは
「姿勢」とは習慣的な動きの積み重ねで作られているものです。
なので、姿勢を観察するだけで普段からどんな筋肉群を使いながらどんな動きを習慣的に行なっているのか、ある程度予測することが可能です。
特に自律神経ケアの場合、「呼吸パターン」が大きく影響していると考えていて、横隔膜を使ったゆっくりと深い呼吸ではなく、首・肩・背中などの呼吸補助筋に頼った呼吸パターンだと、首・肩・背中の筋肉を普段から酷使することになるため、姿勢や呼吸の仕方にも偏りが出てくるのです。
それを姿勢観察や筋パフォーマンステストという形でチェックしていきます。

※パフォーマンステストの一例
普段からよく使っている筋肉はどのテストをさせても大体目立ちます。
いくつかのテストを組み合わせていき、より優勢になっている筋群を特定した後は、実際にどの程度固くなっているのか?硬いだけじゃなく、短くもなってしまっているのか?これらを見極めていきます。
一気に緩む神経筋反射テクニック
硬さが目立っている部位には神経筋反射テクニックを使って筋緊張を緩めていきます。
方法は「等尺性収縮後弛緩」といって、軽い力で抵抗運動をさせて一気に力を抜く方法です。
これで緊張している筋肉は大抵緩み、可動域は増え、痛みも減ります。
自律神経系の反応として期待できるのは、交感神経活動が抑制され、呼吸が浅くなり、心拍の変動が回復するなどがあると考えています。
受講生のほとんどが初体験のテクニックでしたが、やはり事前学習動画の効果もあり、皆さんバッチリと習得されていました。
背骨に対する徒手療法とは違ったカラダの反応を体験していただけた方と思います。
後半は弱っている部位のエクササイズもみんなで一緒に大盛り上がりでした!

いよいよ次は上腹部・下腹部の内臓不調に対する筋膜ケアの講座になります!
皆さん、しっかり事前学習動画で予習しておいてくださいね!
JMF自律神経ケアセラピスト養成コースの案内登録はこちら▼
JMF自律神経ケアセラピスト登録